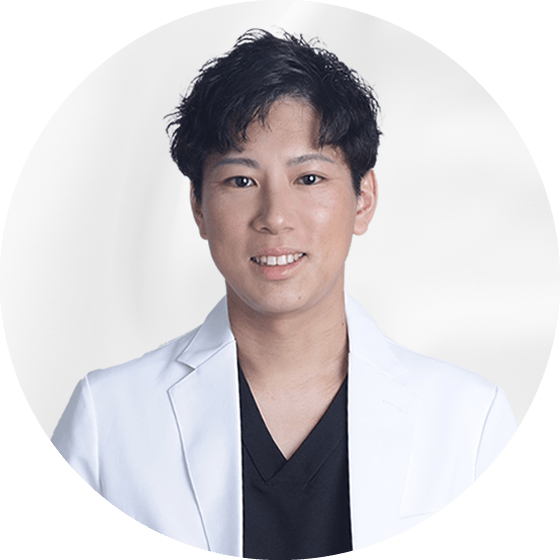医師紹介
Doctor



はじめまして。eクリニック名古屋院の服部健人と申します。
目元整形やクマ治療を専門としております。
また、前職ではより多くの患者様のニーズに応えられるよう、ダウンタイムの少ないヒアルロン酸治療にも力を注いできました。
美容医療の魅力は、コンプレックスを克服し、前向きに人生を送る一助になれることであると考えています。
これまでの経験を活かしながら、高い技術力を有した先生方とともにさらに成長することで、ハイクオリティな治療を低価格に、より多くの患者様に提供し満足していただけるよう精進していきます。
まずはしっかりとお悩みを共有し、皆様が理想の自分に近付けるようお手伝いさせていただければ幸いです。
皆様のご来院を心よりお待ちしております。
SNS Links ドクターのSNS
略歴
-
2015年
産業医科大学医学部 医学科卒業 -
2015年
杏林大学医学部付属病院
初期研修医 -
2017年
杏林大学医学部付属病院
消化器・一般外科入局 -
2019年
聖隷浜松病院 外科 -
2021年
杏林大学医学部付属病院
消化器・一般外科 -
2022年
湘南美容クリニック -
2024年
都内美容クリニック -
2024年
eクリニック名古屋院 副院長就任
資格・専門医
- 日本外科学会外科専門医
- 日本抗加齢医学会専門医
- 日本医師会認定産業医
所属学会
- 日本美容外科学会(JSAS)正会員
- 日本外科学会 正会員
- 日本抗加齢医学会 正会員
Interview
インタビュー
患者様が自分の家族だったら、どうすすめるか
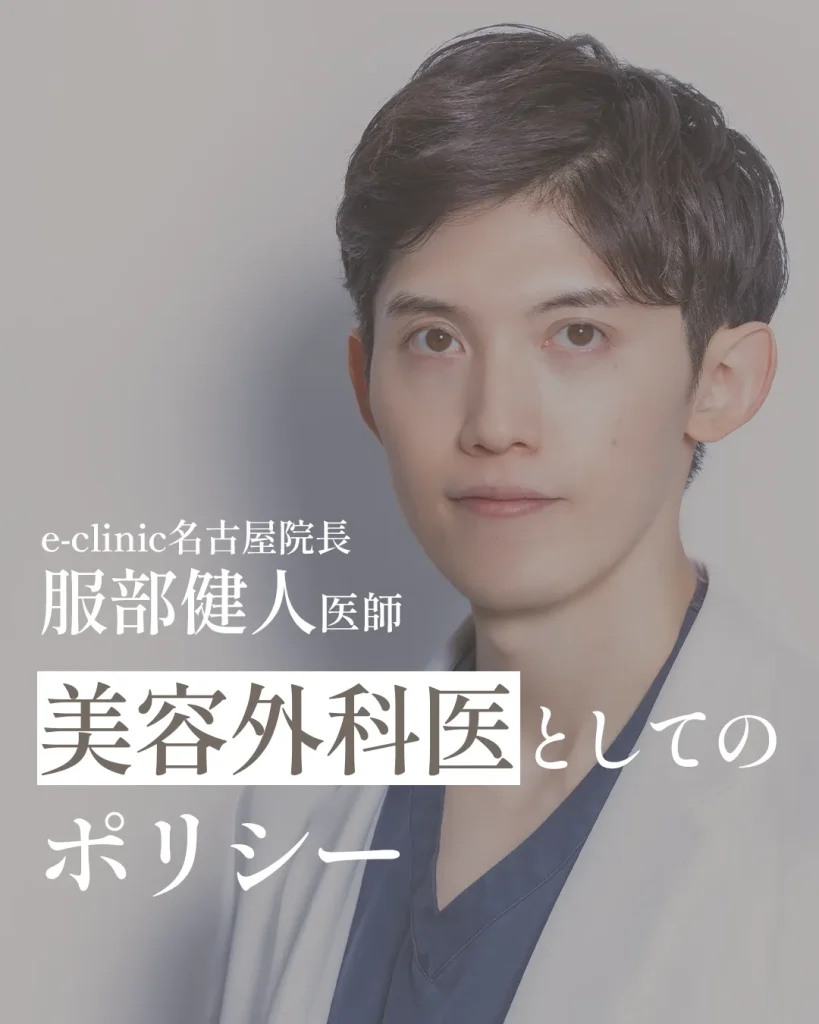
美容医療は、希望をかなえることが大前提。でも、その希望が本人にとって本当にプラスになるのかどうかは、慎重に見極めたいと思っています。 僕自身が診療で大切にしているのは、「もしこの人が自分の家族だったら、すすめるかどうか」という判断軸です。 ご希望が多くても、ダウンタイムやリスク、将来的な不自然さが想定される場合は、きちんとお伝えして、お断りすることもあります。必要以上に盛った施術や、年齢や骨格に合わない整形は、むしろご本人の魅力を損なうこともある。 だからこそ、最小限で1番美しい選択肢をご提案することを常に心がけています。
自分自身の技術を、止まらず磨き続ける
僕は毎日の診療で技術を磨くことはもちろん、患者さん一人ひとりと真摯に向き合うことを第一に大切にしています。技術は日々の施術で磨かれていくものですが、その技術をどう活かすかは患者さんとの対話があってこそだと感じています。 周囲の医師たちからの意見や助言を積極的に取り入れることで、自分の施術をアップデートし続けています。 グループ内外問わず、定期的に症例について意見を交換しています。彼らの経験や見解を聞くことで、自分では気づかなかった視点や改善点が見つかり、それを手術に活かすことができるんです。 また、学会や勉強会で得た最新の知見や技術を共有することで、自分の引き出しが広がっています。 患者さんの満足度が上がることが何よりの喜びです。毎日が勉強であり、挑戦の連続。僕にとって、美容医療の技術は止まることのない旅路です。
「海外風をそのまま」ではなく、日本人に合った美しさを
いまはSNSなどを通じて、海外の流行や強めのデザインが人気になることもあります。 でも僕は、それをそのまま輸入して施術に活かすことには、あえて慎重になります。日本人には、日本人らしい顔立ちや価値観があります。 そこに無理なく馴染む「自然さ」「調和」が、美容医療において一番大切なことだと思っています。施術を考えるときは、顔のパーツだけでなく骨格や全体バランス、表情のクセ、雰囲気、服装、人柄までも見て判断するようにしています。 そうすることで、その人らしさが残る、違和感のない整形が実現できると思うんです。腫れや傷痕、ダウンタイムの出方も含めて、できるだけ患者さんの生活に“ちゃんと馴染む整形”を目指しています。
治療して終わりじゃない。ずっと安心して相談できる関係を
僕は、初診で来られた方が「ここなら何でも話せそう」と思ってくれるような雰囲気づくりを大切にしています。堅苦しくなりすぎず、ちょっとした雑談を交えながら、不安や迷いも含めて話してもらえるようにしています。 たとえば「親族の結婚式があるから、そこに間に合わせたい」といった具体的な背景があれば、仕上がりのタイミングを逆算してご提案したり、必要な手順を明確にしたりと、目的に合わせた施術を組み立てます。 また、施術後の不安にもすぐ対応できるよう、LINEやDMでのご相談にはできるだけ迅速に対応しています。 休診日でも、急な不安があれば対応することもありますし、施術後のちょっとした変化にも「これは大丈夫か」をしっかり判断してお伝えするようにしています。治療はやって終わりではありません。むしろ、終わってからの時間の方が、その人にとって大事になる場面も多い。 だからこそ、長く信頼して通っていただける関係性を築けるよう、丁寧な対応を続けていきたいと思っています。